私が診断書をもらうことをおすすめする3つの理由
ご質問をいただきました。
「化学物質過敏症は治療法があまりないと聞きます。それでも病院に行く意味はありますか?診断は必要ですか?病院に行くのも辛いので迷っています。」
この疑問、私自身も何度も感じてきました。
私が発症したころ(2009年)、化学物質過敏症は今よりもさらに知られておらず、病院に行っても心が折れるような対応に、「もう行かなくてもいいかな…」と何度思ったか数えきれません。
それでも思い直し、最終的に専門医を訪ね、診断書をもらいました(2013年)。
その経験から、私が診断書をもらうことをおすすめする理由が3つあります。
①他の医療機関で理解されやすくなる
たとえば、「待合室にいられない」「使える薬剤が限られている」など、自分の状態を医師や看護師に伝えても、診断書がないと信じてもらえないことがあります。
実際に「それ、どこかでいわれたんですか?」と聞かれたことも。
待合室でフラフラになっていたとき、気づいた看護師さんが順番を早めてくれたのですが、医師に「なぜこの人が先なの?」と戻されてしまった経験もあります。
でも、診断書があると対応が一変。まるで“免罪符”のようだと感じました。
②家族や職場など周囲の理解が得られやすい
診断を受けたあと、職場の皆さんに「こういう診断を受けました」と伝えました。
それまでなんとなく「調子が悪そう」と思っていた方たちも、医師による診断があることで受け止め方が変わり、「じゃあ、どうサポートしようか」と一歩踏み出してもらえるようになったと感じています。
「医師が診断した」という事実が、周囲への説得力となり、人間関係を円滑にする助けになると思います。
③専門医から具体的なアドバイスがもらえる
治療法がないと思っている過敏症の方は多いですが、病気に対して薬物投与や手術だけが治療ではありません。
むしろ、日常生活をどのように送るか、食事は、運動は、といった、本来医師が指導する内容がどの病気にも大切であり、特に化学物質過敏症には重要だと私は思っています。
私が専門医にかかったときは、生活の様子を丁寧に聞き取ってくれました。
そこから私の「思い込み」や「生活の癖」に気づき、少しずつ改善へと繋がったと思います。
⸻
遠方の専門医に診断してもらっても、日常的には医師に相談できない方も多いと思います。
私も診断書をもらうために東京まで行きましたが、当時は地元に専門医がいなかったので日常的な相談や体のケアは鍼灸師の先生と行なっていました。
医師と日常的に話せないのは残念でしたが、診断書をもらうことの効果がこれだけあれば、もらうに十分な理由だと思っています。
そのうち地元にも専門医が現れ(2016年)、今は定期的に診察してもらっています。
⸻
病院に行くのが辛いあなたへ
そうはいっても「化学物質に満ちた病院に行くのは、本当にしんどい」――その気持ち、よくわかります。
私も体調の良い日を選び、「今日は行くぞ!」と覚悟を決めて病院に向かっていました。
でも、行った先で曝露してしまい、呂律が回らず、頭がぼーっとして、医師とうまく話せないこともありました。
そんなときに役立ったのが「事前に自分の症状をメモして持っていくこと」。
今の状態を言葉にまとめておくだけで、伝えたいことが格段に伝わりやすくなります。
⸻
詳しくは、こちらの動画でもお話ししています。
無理せず、自分のペースで体と相談しながら進んでいけたら、それで十分です。
あなたが少しでも安心して、次の一歩を踏み出せますように。
『大丈夫、きっとよくなる。化学物質過敏症の私がつくった製品wacca(ワッカ )』

たくさんの人が化学物質過敏症の現状を知ってもらうために、応援してくれています。
このバナーをクリックしてくれるだけでこの応援の輪がどんどん広がっていきます。
ご協力ありがとうございます。


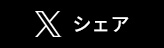
コメントを残す